今回は少し目先を変えて数学の話から始めてみよう。
「成功する確率が4%の独立な試行を10回行った時、少なくとも1回成功する確率はどれくらいか?」という問題について考えてみてほしい。
先に種明かしをしておくと、これは「ある自治体職員が在職中に一度でもシステム担当となる確率はどれぐらいか。ただし職員数は5000名、200件の情報システムを有し、一つのシステムに職員1名が担当する。なお、職員の在職中の異動は10回とし、異動先や職務内容は前の部署とは無関係とする。」という問題と同じである。かなり具体的な想定が含まれるが、私の関与する自治体では概ねこのような状況だ。
これは二項累積分布関数を使って計算でき、答えは約33%となる。すなわち、三人に一人が在職中に一度は情報システム担当となる。逆に残りの二人は情報システムと関係を持つことなく役所人生を終えるという言い方もできる。
ちなみにシステム寿命を5年と仮定し、5年毎のシステム更改に遭遇する確率を同様に計算すると、7.7%となる。つまり約13人に一人だ。この割合をどう考えるかによるが、さほど頻繁に遭遇しない事態に備えて個々の職員にスキル向上を求めるのは酷なのかもしれない。
もっとも、情報システム担当になる確率もゼロではない。いざ自分がそうなった時に「何をどうしていいのか判らない」状態では、本来、一線を引くべき相手であるシステムベンダーに対して過剰に依存したい意識が芽生えるのは無理もないところだろう。結果、発注者である自治体はベンダー評価の客観性を失い、次第に調達の公平性が失われていくことにつながる。
案外このように単純な事実にすら気づいていない組織は多い。そのため情報化投資を属人的な対応でやり過ごすのではなく、組織全体の事業と考え、組織そのものの能力を高めることで課題に向き合う姿勢が必要だろう。これを実現するために、組織を内側から変えていくことが当面の私の取り組みである。
佐賀県のガイドライン
これらの取り組みの一環として、佐賀県では情報化投資に関する3つのガイドラインを整備、運用させている。
情報化企画ガイドライン
情報化投資のための予算要求を行うために、情報化企画から参考見積徴収を経て予算要求、予算査定までの手順を示したもの。
調達・契約ガイドライン
予算に基づく適切な調達を行うために、調達仕様書作成から入札事務手続、委託契約までの手順を示したもの。
プロジェクト管理ガイドライン
情報システムの導入・保守・運用におけるプロジェクトの品質や進捗等を管理するための手順を示したもの。
これらのガイドラインの狙いは「事務の標準化による業務品質の維持」にある。そのため、職員が情報化投資に関する事務を遂行するための作業手順書として使うことを想定して整備している。
例えば、個々の作業は処理しやすい単位で分解され、事務フローとして時系列に並べて記述しており、職員自身が次に何をすればよいのかを理解しやすいように記している。また、分解された作業には、「いつ、いつまでにその作業をするのか」「作業着手前に何を準備しなければならないのか」「準備物を使ってどのような作業をしなければならないのか」「作業完了後にはどのような生成物ができあがるのか」を示し、誰がやっても同じような手順で、同じような成果が得られるように配慮している。
事務フローを示すと、職員は個々の作業が連鎖していることに気づく。そのため、今の作業の生成物は次の作業の準備物として扱われるということを意識し、先を見通した作業を進めることができる。
ガイドラインを用いた知のサイクル
自治体の情報化投資においてガイドラインを整備し運用したのは、平成15年の高知県が最初だったように思う。その後、全国で同様のガイドラインが整備され運用を始めたものの、現時点で定着し続けているところは少ない。それはガイドラインを用いた運用にもそれなりの労力が必要だからだ。
一般的に行政職員は、過去の多くの事例を俯瞰して、それらを踏まえて仕事をやり遂げるという「帰納的」なアプローチが得意だ。それは職員が頻繁に「何か参考になる事例はありませんか」と尋ねてくることでもよく分かる。ただ、職員は良い事例と悪い事例の目利きができない。そこで、私のような専門人材がガイドラインに基づく運用を促しながら、良い事例を収集、体系化して職員にフィードバックすることが必要になるのだ。これが「ガイドラインを用いた知のサイクル」だ。
情報化投資は難しい。しかしガイドラインと良い事例が適切に組み合わされば、個々の作業は容易に遂行できる。さらにシステムが稼働し、問題解決ができた時の喜びは大きい。このような「成功体験の積み重ね」により組織がさらに成長することを期待したい。
※本稿は私個人の意見であり、私が所属する機関の意見を代表するものではありません。
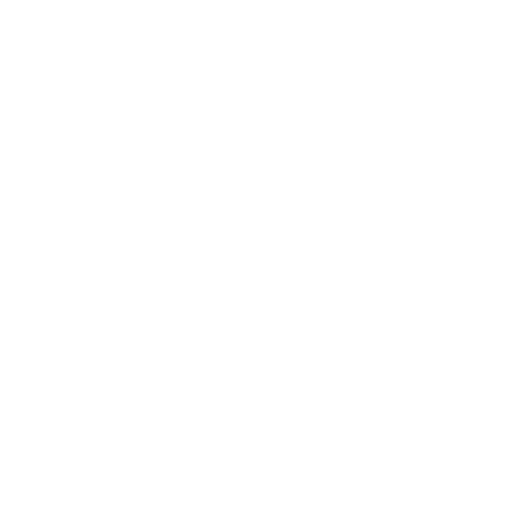 Hiro KAWAGUCHI Laboratory
Hiro KAWAGUCHI Laboratory 
