はじめに
前回「ふるさと納税から見る自治体間競争の未来:政策編」という記事を書いて、政策に対して住民税の納税先を変えることによる意思表示の可能性について考えてみた。
この中で、ふるさと納税における返礼品競争の問題についても考えてみたので、その過程を示すこととしたい。
経営学の観点から
「返礼品競争が過剰になっている」という話は、ふるさと納税をテーマにすると必ずついて回る話題である。しかしこの問題は、経営学の観点から言えば競争戦略のひとつでしかない。
ふるさと納税者(国民)は自治体にとって「買い手」である。数多ある自治体の中から自分たちを納税先に選んでもらうためには、何らかの手段を用いて買い手を誘引しなければならない。
その手段のひとつが返礼品である。返礼品が差別化の要素であるならば、競争が激化するのは当然の話である。
ところが自治体が目指すゴール次第で、この競争の捉え方はいかようにでも変えることができる。その戦略がいい加減なので、返礼品競争におかしな解釈がされてしまうのだ。
自治体が目指すゴールとは(ファーストステージ)
忘れてもらっちゃ困るけど、自治体だって事業を営む主体である。営利の要素が薄いだけで、本質的な戦略は営利企業のものと違いはない。
そういう意味で、ふるさと納税は自治体が営む事業を構成する一部ということになる。
では、自治体はふるさと納税を通じて何をゴールにしているのだろうか? これは自治体の考え次第だが、いくつかのステージに分けることができるだろう。
純粋に歳入の増加がゴールの場合
本来のふるさと納税制度はこれが目的とも言えるだろう。この場合、ふるさと納税の件数と純歳入(寄付金額-返礼品の原価)の最大化を目指すために、どうするのかを考えるべきだろう。
しかし、いきなり件数や純歳入を高めることは難しいのも事実。そこで以下のような中間指標となるゴールを設定して取り組むことも有効だろう。
自治体の認知度を高めることをゴールとする場合
全国には約1,800の自治体がある。その中でもともと縁の薄いふるさと納税者から寄付を勝ち取る(あんまり好きな表現じゃないけど)ためには、まずその存在を認知されなければならない。
そこで認知度を高めること自体をゴールにする場合もあるかもしれない。ということで、手っ取り早く認知度を高めるために、魅力ある返礼品を用意することになるのだろう。もちろんそれは悪いことではないし、ふるさと納税者との最初の接触ポイントは案外こういうところなのかもしれない。
ただ、これだけをゴールにしているのならば、悲劇だ。
この事例はすでに解消されているものの、価値が明らかで換金性が高いものとなると、返礼品とは言えない。またこの自治体は「実入りの高い自治体」という認知度は高まるが、その関係は非常にドライなものになってしまう。自治体の気持ちは判らなくはないけど。
この事例、必死なのはわかる。個人的には否定するものではない。せっかくならばこれだけをゴールにしないで欲しいと願うばかりである。
これらの事例とは別に、おおよそ「宣伝のため」としているところは、実際にはその先のことを考えていない事が多い。宣伝は手段であって目的ではないのだ。
地域の特産品の認知度を高めることをゴールとする場合
返礼品に地域の特産品を充て、認知度を高めることをゴールとすることもある。考えようによっては返礼品自体、自治体が仕入れた上で送っているわけだから、単純に地域の売上には寄与するし、特産品の販売チャネルが全国に拡大しているのだとも言える。
まぁ、いわゆる「単純にウケる」特産品がない自治体はこれだけでハンデを負っているようにも感じるけど。
ただ、残念なのは返礼品としてアピールしているものを見ると、食肉とか海産物ばかりがふるさと納税者に評価されているようで、それはそれで切ない気持ちになる。(あ、私も海産物を返礼品としていただきましたので、偉そうなことは言えません)
そもそも、返礼品を目当てにしているふるさと納税者は、米沢牛と松阪牛と近江牛と佐賀牛と宮崎牛の違いを意識しているのかというと、そのあたりは怪しい気がする。
自治体が目指すゴールとは(セカンドステージ)
ということで、実はほとんどの自治体はここまでで思考が止まっている。これではせっかくのふるさと納税制度が双方で活用されているとは言いがたい。
仮に歳入の増加を目的とする場合でも、瞬間的な成果ではなく安定した財源とするのならば、継続的な寄付先として魅力を持たせなければならないはずなのだ。悩ましいのは、その魅力が返礼品であるかぎり、他自治体との間の競争に巻き込まれて、消耗戦になってしまうところにある。
返礼品を目当てにしているふるさと納税者は、より実入りのよい納税先を選んで動き回ることになるので、ここからは返礼品の内容とは別の要素を盛り込んで、ふるさと納税者から特別なパーミッションを得るための戦略を立てる必要がある。
自治体への関心を高めてもらうことをゴールとする場合
ブランド牛なら何でもいいとする考えを持つ人々から、(例えば)佐賀牛でなければならないと思わせるには、返礼品ではなく納税先の自治体そのものに関心を持ってもらうことを目指さなければならない。
きっかけは曖昧でも多少不純でも構わない。ただ、その特産品がどのような土地で生み出され、他と何が違うのか。そして、その地域ではどのような取り組みをしているのか、どのような人たちがいるのかなど、伝えなければならないメッセージは多岐にわたる。
ちなみに私はふるさと納税の業務を自治体のどの部署が担っているのかに興味を持っている。これにより、その自治体がどのような意図でふるさと納税に取り組んでいるのかが判るのだ。
例えば、地域振興に関連する部署だとふるさと納税を地域振興の手段として捉えていると見ることができるし、観光関連の部署の場合もある。政策企画の部署の場合には、かなり広範囲に戦略を練っているようにも見受けられる。
一方、総務部や税務課などの部署の場合もあり、その場合には受け身のスタンスであるか、そもそも「ふるさと納税」という言葉の意味だけで担当を割り当てているような、少し力不足の印象を受けることもある。
行政機関の場合「組織は戦略に従う」ことが一般的であるため、これだけで戦略的な取り組みの有無を推測することができるのだ。
自治体との何らかのコネクションを持つことをゴールとする場合
地方の自治体の場合、高齢化や人口減少問題を解決するために、Uターン、Jターン、Iターンなどの移住促進を政策に掲げていることが多い。
後述する「体験」につなげるために、まずは自分たちの地域や自治体となるべく深い関係になってもらうことをゴールにする取り組みも、ふるさと納税をきっかけにできるようになるのだ。
マーケティングの用語でこれを「リード」という。このリードをどれだけ強く、太くしていくのかの考え方やテクニックは、民間企業でも同じである。
少なくとも、今まで接点が無かった個人とコンタクトが取れるのは自治体にとってはチャンスである。このチャンスを逃してはならない。それが返礼品目当てであったとしても、何らかの興味を持っているのだから。
自治体において何らかの体験をしてもらうことをゴールとする場合
コネクションを築き上げることにより、継続的な寄付も期待できるようになるかもしれない。ただ、観光や地域振興の立場から言えば、実際に現地に足を運んでもらい、現地で何らかの体験をしてもらうことも有効だと思う。
実際、いくつかの自治体では返礼品に現地の施設の利用権や宿泊券、現地での体験ツアーへ参加できる権利なども提供されている。
移住促進などは、いきなり移住先を決めることはないので、体験、経験という要素は欠かすことができないだろう。そのきっかけがふるさと納税であるというのは、今後現実味がある話だと思う。
このように漠然とした「宣伝」ではなく、ふるさと納税をきっかけに政策を実行していく戦略を立てることで、この制度の有効性は格段に高められると思う。
その際に、整備すべきはマーケティング・コミュニケーションを管理する仕組みだ。営業の世界ではSFAと呼ばれるシステムがこれに該当する。要は見込み客や取引中の顧客を管理し、顧客の満足度を高めていく考え方である。
ちょっとだけ私の経験を書いておく。
私は2009年4月に高知県に赴任し、その後数年間高知県で過ごした。着任した年の住民税は前の住所地に納税していたので、その差額を埋めるべく高知県庁に寄付をしたのが、初めてのふるさと納税体験である。
まぁそれほど多額の寄付をしたわけではなかったし、返礼品という制度があることも知らなかったのだが、高知県庁からある日返礼品が届いて驚いた。
返礼品が「鳴子」だったのだ。鳴子というのは、よさこい祭りで踊るときに手に持っているアレである。おそらく高知県庁は良かれと思って、そして自分たちの文化に誇りをもってこの返礼品を選んでくれたのだと思うが、当時の私にとっては無用の長物でしかなかった。
ミスマッチだったことは仕方ないと思うが、私自身がマーケティング・コミュニケーションの観点でふるさと納税にどう取り組むべきかを考えるきっかけとなる良い経験だったと思う。(ちなみに高知県には継続してふるさと納税していますが、現在は状況が大きく変化していることを付記しておきます)
自治体が目指すゴールとは(サードステージ)
セカンドステージとされるゴールは、どちらかというと返礼品をうまく活用した地方の自治体向けに設定するゴールなのかもしれない。
これから考えるサードステージは、以前書いた「ふるさと納税から見る自治体間競争の未来:政策編」に関連する取り組みである。ベースとなる考え方はそちらに書いている。
自治体の考えを理解してもらうことをゴールとする場合
私の考えのベースは「地方創生は横並びではなく差別化により実現するべき」というものである。そして、市民と自治体との関係は地域的な制約で縛られるものではなく、もっと多様化したものに変化していくことが、結果的に互いの競争力を確保し成長・成熟していける道なのだと考えている。
そのためには、他の自治体と何が違うのかをアピールすることが必要となるだろう。
これは私の主観が交じるけど、これまで地域のあり方は政府が決めていて、自治体はその下請のような立ち位置に置かれることが多かった。しかし実際、政府は地方のことを十分に理解した上で施策を考えているとは言いがたい状況が続いている。また、政府の能力が低下しつつあるように感じているし、今後その状況が改善されるようにも思えない。しわ寄せは自治体に向かってくる。
ならば、自治体は自らの判断で地域をどうしていくのかを、今までよりもさらに主体的に考えていかなければならないのだ。行政サービスの担い手としての「執行者」の立場だけでなく、政策を立案する「経営者」の立場がさらに重要になると予想する。
ふるさと納税が自治体を「応援する」ための寄付金の役割を有するのならば、応援の対象は「差別化された政策」なのである。事実、ふるさと納税を行う際に、寄付金の使いみちをふるさと納税者が選べる自治体もある。現在は「地域の自然を守る」や「子供の未来のために」など、比較的緩やかな領域で選べることが多いが、どうしても自治体として取り組みたい施策があるのならば、それらをきちんと示した上でふるさと納税を受け付けることが必要だろう。
自治体の考えに共感してもらうことをゴールとする場合
さらに、差別化された政策に対する寄付であるならば、その後、寄付金がどのように使われたのかを示すことも必要だ。
その上で、さらに政策に対する共感を醸成しながら、継続的なふるさと納税を求めていくことができれば、全国から賛同する力を得ながら、自治体は自ら考える能力を養うことができるようになるだろう。
まとめ
様々な自治体がふるさと納税を通して、試行的な取り組みを実践している。私は引き続き、そういう自治体を支援していきたいと考えている。
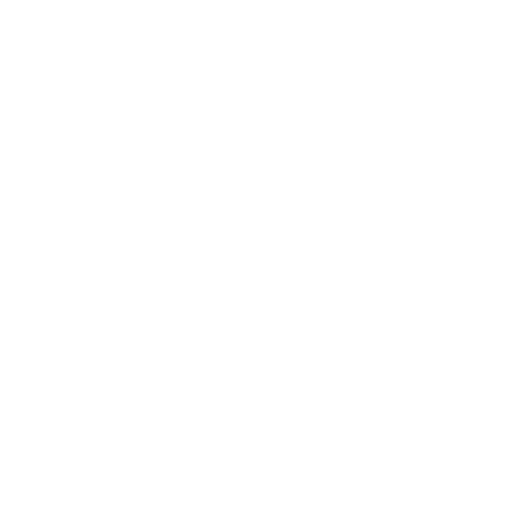 Hiro KAWAGUCHI Laboratory
Hiro KAWAGUCHI Laboratory 